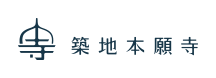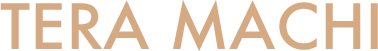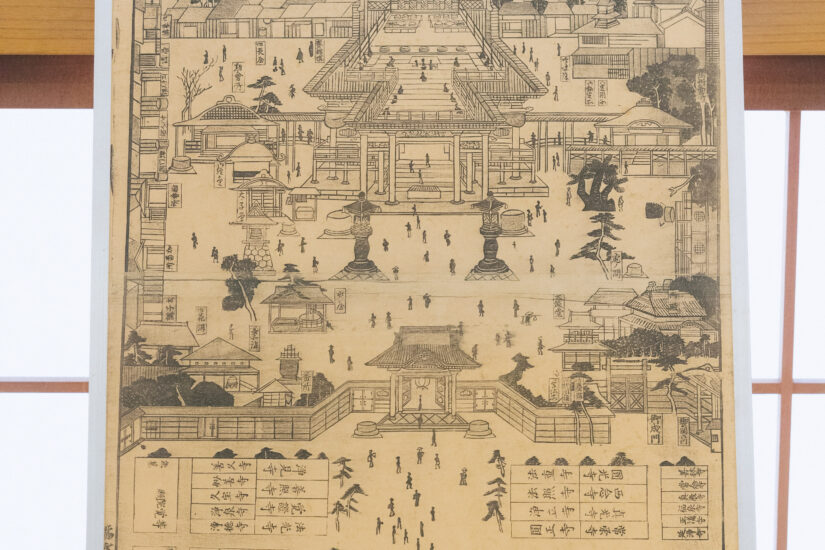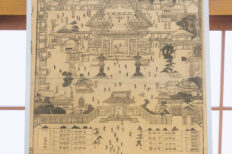住職:南條 了瑛 師(なんじょうりょうえい )
■幼い頃から「面白い」「好きだ」と感じていた浄土真宗の教え
寺で育ち、幼い頃から父の様子を側で見て、ご門徒様と接してきましたから、小中学校の頃には、将来はこのお寺の住職になるのだという自覚があり、そのことを自然に受け入れていました。そこには、私自身が仏教をおもしろいと感じ、また浄土真宗の教えが好きで、自分に合っていると思っていたことが大きかったと思います。浄土真宗のみ教えは、人間の弱い部分をそのまま受け止めてくれます。頭でわかっていてもそうできないことや、理屈だけではうまくいかないことなど、リアルな部分をきちんと拾ってくださり、無条件で受容してくださる仏様だということを、私自身が救いに感じていたのだと思います。
高校卒業後は京都の仏教を学べる大学に進学。そこで、同様に将来僧侶になる学友たちと出会い、仏教について共に学べたことは今でも私の宝ですね。その後、「開かれたお寺」「地域に根ざしたお寺」の活動に関心を持ち、同大学の大学院、実践真宗学研究科に進みました。
■古くからのご門徒様を大切にしながら、新しい出会いも
「開かれたお寺」への関心から学びを進め、ここで坊守とも出会いました。当時私が理想としていたことは、実際に住職になる過程で少しずつ変化し、今はまず、ご門徒様に寄り添うお寺でありたいという思いを強くしています。しかし同時に、仏教や浄土真宗の教えを身近に感じてもらいたいという思いもあり「TERAKOYA(寺子屋)」を運営。インスタグラムなどのSNSツールを用い、広くお寺の門戸を開いてきました。
「TERAKOYA」では、聖典講座や、小さな子どもとお母さんに向けた音楽教育法「リトミック教室」、寺子屋音楽教室「ソルフェージュ教室」などを開講。これまであまり仏教に触れてこなかった子育て世代の皆さんがお寺を訪れるきっかけの場にもなっています。
また、坊守が直接お話しながら描く参拝記念イラストも大変人気で、こうした場をきっかけに聖典講座に起こしいただく人もおられ、うれしく感じています。
■外国人に仏教を伝える活動
築地という土地柄、多くの外国人観光客や、日本に住む外国ルーツの方々が訪れます。そうした人々に仏教や浄土真宗を伝えていくことは、これから必ず力を入れていくべきことだと考えています。私自身、学生時代には米国バークレーの米国仏教大学院に1年間留学し、今は築地本願寺で外国人のための「英語法座」を企画運営しています。ゲストスピーカーと連携しつつ、私自身も英語で法話を行っています。また、英語は個人的にも好きで、ライフワークにしたいと考えています。大学では英語で仏典を読む講義を担当し、築地本願寺新報では英語記事の連載も続けさせていただいています。さらに法重寺でも、インバウンドの方がお寺を体験できるような企画を検討しています。例えば、マインドフルネスや「正信偈」のお勤めなどを通じて、気軽に仏教に触れていただける場を設けたいと考えています。
■「ペット墓」を仏縁に出会っていただくきっかけに
もう一つ、ご門徒様や時代の要望を受けて取り組むことになったのが「ペット墓」です。あるとき、ペットを供養したいという思いを持つ方からお問い合わせをいただきました。浄土真宗は生きとし生けるものすべてを救う阿弥陀如来の本願を私ごととして聞く教えです。亡くなったペットをご縁にお経をあげさせていただいた際、その方がボロボロと涙を流される姿を目にし、ペットが飼い主にとって家族同然の存在であることを強く実感しました。その出来事が、ペット墓を整えるきっかけとなりました。今後、このペット墓を通して少しでも多くの方が仏縁に出会い、浄土真宗の御教に触れていただければと願っています。
お寺というのは、どなたにとっても開かれた場所です。これからもご門徒様とともにある法重寺であることを大切にしながら、同時に多くの人がみ教えを知るきっかけの場となるよう努めていきたいと思います。