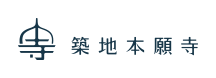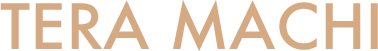■縁を紡ぐための、核たる場所としての在り方
浄土真宗では僧侶が地域共同体の中に入り布教し、そこで教えに帰依した村の長たちが道場を創ったことに由来する寺院が多くあります。また戦国期には近畿を中心に真宗寺院を核として寺内町という自治都市が形成された歴史があります。その後豊臣政権、それに続く江戸幕府の寺院管理政策によって都市では寺町が形成され、民衆の住む場所と寺は離れることになります。特に都会の寺ではご門徒の住まいと寺が近隣であるということは稀です。西照寺は昭和初期にこの地に移転してきたため、寺と門信徒という関係で地域と関わるということは難しい現状があります。
現代における寺の果たす役割を考えると、門信徒ではない方々をも地域における新たな中間的なコミュニティの核となれるのではないかと考えています。寺は本堂や境内など、広いスペースがあります。そこを地域の人々のサークルや勉強会、イベントなどに活用してもらえれば、寺の敷居も低くなり、気軽に入れる場所になると思うのです。
また西照寺には「サンガの会」というご門徒さんの集いがあり、ご門徒さんが自主的にイベントや旅行会などを企画してくれています。門信徒のみなさんは互いを「寺友(てらとも)」と呼び、その集いを楽しんでくれています。これは住職としては大変有難いことですし、嬉しいことでもあります。
寺友という関係は意図的に作られたものではなく、ご門徒のみなさんが寺を縁として出逢い、緩やかにそのご縁を紡いできたことによって生まれたのだと思っています。学生から付き合いの続く友人を「くされ縁」などということがあります。そのように人と人とが出会い緩い関係性を紡いで繋がっていくことが、今必要とされているのではないでしょうか。私は寺という場所は、そういったご縁を紡ぐための、一つの核となる場所でありたいと思っています。
■他人に寄り添うことの難しさを自覚し、それでも人の心の栄養の素になりたい
元来、僧侶が人々に伝える教えは、人々が抱える苦悩からの解放です。それは現代においても変わりません。僧侶はご葬儀の場で大切なご家族を亡くした方の深い悲しみの中に身をおき、ご法話もさせていただくのですが、その中で深く辛い悲しみに寄り添う言葉の難しさを痛感します。私自身妻を亡くしているのですが、闘病中には余命告知を受け覚悟を決めていたつもりでありましたが、その時が至った時にこれほど涙が流れるかと思うほど涙があふれ出てきました。その後周囲の方々が気遣ってかけてくださる言葉が、逆に辛い時期もありました。
東日本大震災の後、被災地に立った僧侶を取り上げた雑誌の記事に「沈黙」という言葉がありました。沈黙せざるをえない厳しい状況の中で、傍にいることの大切さを感じました。厳しい状況の中、心の支えになるのは人の繋がりです。仏教の根本には全てのものが繋がりあっているという縁起の思想があります。
慈悲とは仏教において苦を抜き楽を与えるという意味ですが、慈の原語はマイトリーで友という意味で、悲の原語はカルナで呻きという意味です。呻きうずくまる人に寄り添う友の姿が慈悲という言葉の姿なのです。その寄り添い共感する人があることによって人が苦しみ悲しみから立ち上がり前に進む力を恵まれるのだと思います。
現代社会では、人と人とのつながりは単層的になっていて、その一つの居場所をなくすことによって人との関係性を失う人が増えています。関係性が複層的であれば社会との繋がりは維持されます。寺を核とするコミュニティが心に潤いや活力を与えられる一つの場になれたらと思っています。